【この記事のポイント】
・七十二候のひとつ「蓮始華(はすはじめてはなひらく)」は、蓮の花が咲き始める時期(7/12~16頃)を表す言葉。
・泥の中で咲く蓮の姿に、“生きる力”をみてみよう。
・蓮文様は仏教の象徴の華として、文化財にも多用されている。
・蓮根文様もまた縁起の良い文様として親しまれてきた。
蓮始華(はすはじめてはなひらく)とは?
「蓮始華」とは、二十四節気の「小暑」の次候にあたり、蓮の花がはじめて咲き始める頃を表す七十二候のひとつです。
例年7月12日頃から16日頃までの、ほんの数日のあいだ──
夜明けとともに花びらをゆっくりとひらき、昼には静かに閉じる。
それを4日ほどくり返し、やがて散っていく。

咲ききった姿は、まるで天を仰ぐよう。
けれどその根は、濁った泥の底。
ゆらゆらと不安定な足元に、じっと身を沈めながら、折れることなく咲こうとする。
昼にはまた静かに閉じ、これを四日間くり返して、種をいっぱいつけて散っていく──
そのいのちの姿は、まるで人生の象徴のようでもあります。

泥の中だから
整えられた環境でもない、誰かに祝福された場所でもない。
むしろ、苦しみや葛藤、見通しのつかない日々。
そんな“泥”のような場所にこそ、私たちの根っこは育ち、やがて花を咲かせる力になる。
“整っていない状況”にいるからこそ、光の方へ、光の方へと向かいたくなる。
生きることは、変化することでもあるから、不安定で当たり前なのかもしれない。
泥にまみれた日々の中にこそ、にじみ出る美しさがある。
そんなことを知っている花は──ほんまに、美しい。
美味しくてうつくしい力
そして、泥の中でこそ、蓮は根を張り、茎に栄養を蓄える。そう、あの蓮根(れんこん)。

姿は見えなくても、しっかりと育ち、私たちの身体を内側から整えてくれる恵みです。
ビタミンCや食物繊維、カリウムやポリフェノールなどをたっぷり含む蓮根は、巡りを良くし、肌を整え、余分なものを手放して、私たちを軽やかにしてくれる。
つまり、“美味しくて、うつくしい”人生の力が、泥の中に潜んでいるんです。
文様に込められた意味
仏教では、泥に染まらずに咲く蓮の姿を「清浄」の象徴とし、悟りの花とも称えます。
また、華が咲いた後に、たくさんの実を結ぶことから、子孫繁栄をあらわす縁起のよい文様としても親しまれてきました。
仏教が日本に伝わったそのはじめから──
祈りの場には、蓮の文様がそっと寄り添ってきました。
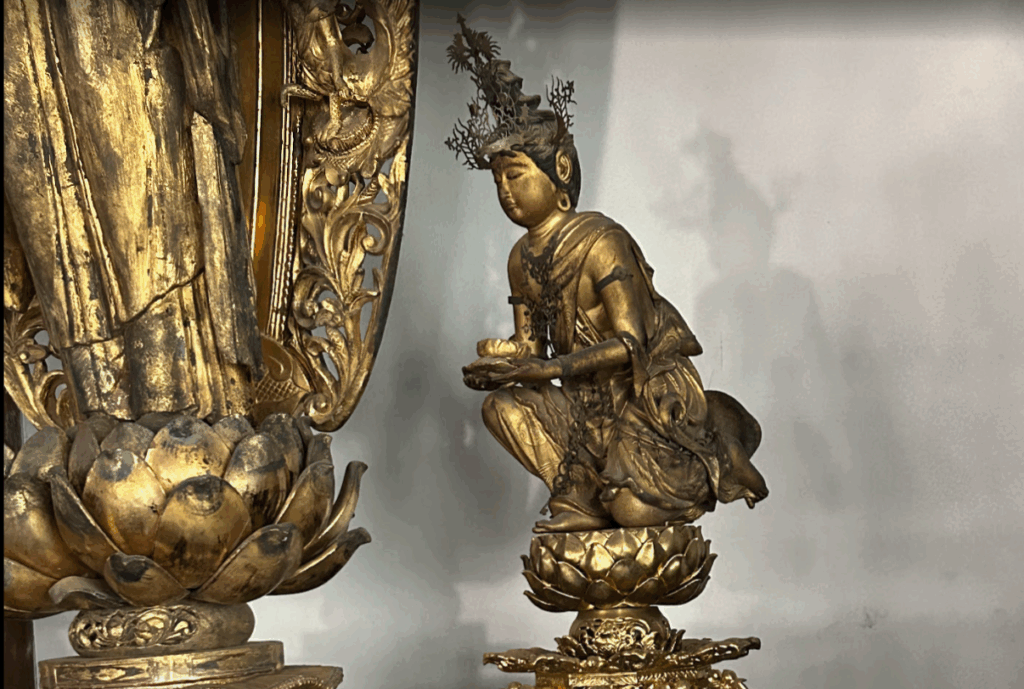
寺院の屋根を飾る軒丸瓦や、仏さまの足元に広がる蓮台(れんだい)にも、蓮のかたちが息づいています。
蓮は、“祈りと繁栄のかたち”として、千年を超える時のなかで、日本の文化に深く根を張ってきたのです。
また、蓮根には多数の穴が開いていることから、蓮根紋様は、将来の見通しが良くなる、子孫繁栄などの意味が込められ、これまた縁起の良い文様です。
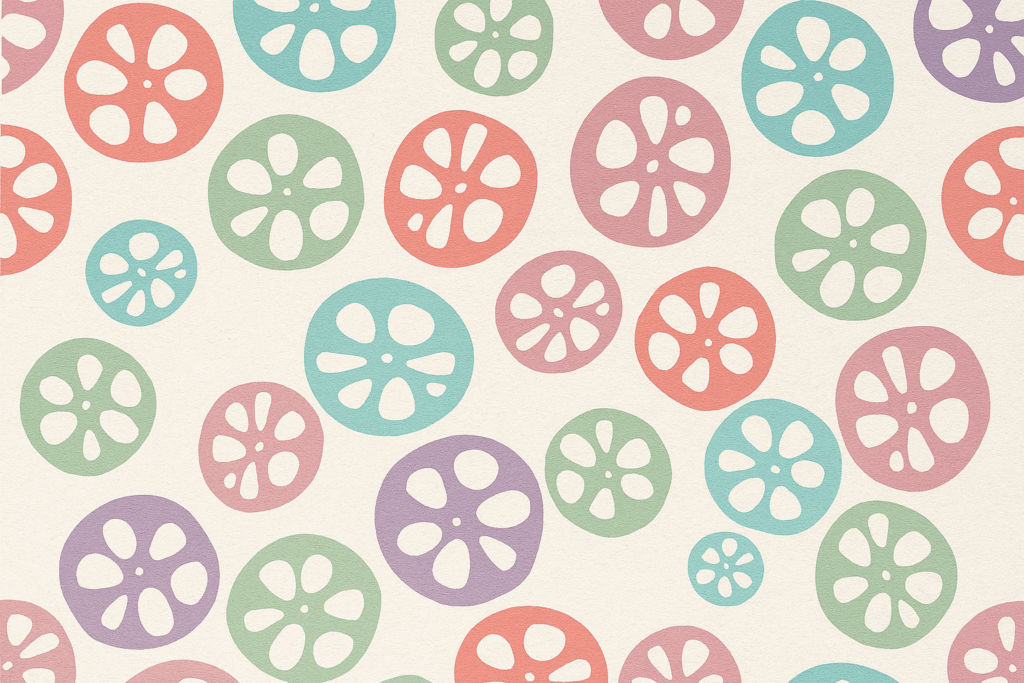
暑さに汗みどろになった時、
不安が押し寄せた時、
心がどろどろになった時こそ、
蓮文様や蓮華文様を身に付けたり、
みほとけに手を合わせて・・・
泥に根ざして咲く華を思い出してくださいね。
そして、あなたの中にも咲くべき花があることを信じて下さい。
それは、あなただけの一輪!








